NEWS お知らせ / お役立ち情報
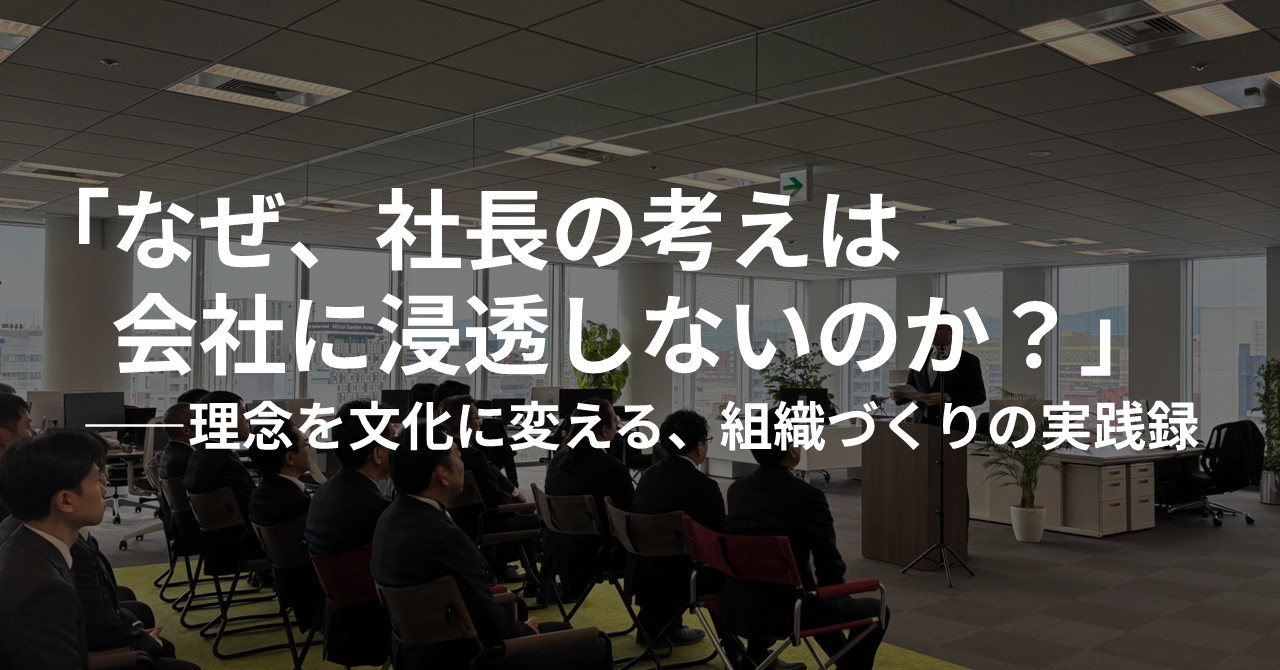
「なぜ、社長の考えは会社に浸透しないのか?」——理念を文化に変える、組織づくりの実践録
【この記事について】
本記事は、代表・平木によるメッセージです。
「理念はあるが、なぜか社員に届かない」「制度を整えても浸透しない」――そんな課題感をお持ちの経営者・人事担当者の方へ向けて、当社が取り組んできた理念浸透と文化づくりの実践内容を、赤裸々に綴っています。
経営理念を“掲げるだけ”で終わっていないか?
人を動かす仕組みは、本当に“共感”まで設計できているか?
本記事では、当社が試行錯誤の中で見出してきた「制度と人をつなぐ仕組み」についてご紹介しています。組織づくりに向き合うすべての方へ、何かひとつでも気づきのヒントをお届けできれば幸いです。
【代表メッセージ】
なぜ、社長の考えは会社に浸透しないのか?組織を動かすための制度はあっても、共感を生む仕組みがなければ人は動かない――。
様々な経営者にインタビューをさせて頂く中で、なぜ福利厚生の施策一つをとっても、従業員の待遇改善の一環であり、そもそも喜んで欲しいと思って実施する施策であるにも関わらず、従業員たちからの反発に合うことを想定して二の足を踏むことになるのか、不思議な思いをしていました。
私は、福利厚生は会社の考え方を社内外に向けて発信する手段の一つだと考えています。きちんとメッセージを発信することで、インナーブランディングにすらなると思っています。ただし実際には、そんなことをするぐらいなら、給料を上げてくれという声が上がる懸念がある会社は少なくなさそうです。
何も福利厚生だけの話ではありません。例えばDXの推進。新しいことをやろうとすると、変わりたくないかつ声の大きい人が改革の足かせになる。割とよく聞くあるあるではないかと思います。JCAは割と新しいことをどんどんやっている方だと思いますが、社員は皆、一生懸命に取り組んでくれますし、割とスムーズに移行できている気がします。
なぜそんな話になってしまうのか?なぜ、この会社の考え方が素直に伝わらないのか?この素朴な疑問が、この記事に書いているような内容を整理したきっかけでした。理念を掲げているのに社員に届かない。そんな悩みを持つ経営者・人事担当の方へ、私たちJCAが取り組んできた理念浸透と組織改革のリアルなプロセスをご紹介します。
~
こんにちは。株式会社JCAの代表を務めている平木です。
私は2005年に新卒でJCAに入社し、16年システムエンジニアとしてシステム開発を行ってきましたが、先代社長(故 佐藤隆社長)の肺がん発覚をきっかけに後継者指名を受けました。
そして、先代社長の急逝に伴い、代表取締役に就任しました。
先代社長は創業者で私たち社員にとってカリスマであり絶対的な指針でした。JCA=先代社長でした。私たちは会社へ帰属する意識ではなく、社長についていけば良いと盲目的になっていたところがあると思います。
その存在を突然失い、そして自分自身がトップに立ってしまった。当時の私は、JCAとはどのような会社で、どのような理念を持っているのかを言葉で表現することができませんでした。
「For You」、「商店の親父」、「自己責任」、「バッファを持て」、「利他」等、先代社長がよく口にされた言葉はあり、社内の共通言語として私たちもよく使っていました。また、先代社長は毎月数時間をかけて、様々な事例を挙げながら、人間力の大切さ、人はどう生きるべきかを私たちに語りました。
それは私たちの中に長い時間を掛けて蓄積されていましたが、いざ社長がいなくなったとき、誰一人として体系立てて明確に説明することができませんでした。
また、私は正直なところ、JCAの経営理念が分かりませんでした。
「この会社は何を成し遂げるのか」
「創業者はこの会社で何をしたかったのか」
「私たちはなぜこの会社にいるのだろうか」
「社会におけるこの会社の価値とは何か」
私自身は、一システムエンジニアとして、何のために働くのか、私の価値は何か、仕事におけるポリシーを私なりに認識し、誇りを持って働いていましたが、私が所属する会社については漠然として分からず、このように、様々な疑問が降りかかって来ました。
先代社長は、私を後継者に指名した理由の一つとして「平木がJCAの本質的な価値を最もよく理解している」と言われました。そんな私でさえ、漠然としか分からなかったのです。そして、社員の数だけ解釈するJCAがあるとすれば、それは恐ろしいことです。空中分解する火種になりかねません。
2021年当時、これから社員を率いていかなければならない、社員を採用していかなければならない私にとって、この指針が持てていないことは致命的なことでしたが、当時は相談できる人がおらず、途方に暮れました。
急きょバトンを受け取って以来、経営者としての私の仕事は何か、価値は何か、何のために仕事をしているのか、一体誰の役に立てているのか、この会社の企業理念や経営理念は何か、本質的な価値は何か、そして私たちは何者なのかをずっと考え続けています。
なぜ、社長の考えは会社に浸透しないのか?先代社長は、少なくとも約20年間、毎月少なくとも2~3時間をかけて、全社員を集めて社長としての考えを発信されていました。その気が遠くなるような労力を掛けても、後継者指名を受けた私ですら、ぼんやりとしたものしか掴めていなかったのです。
未だ道半ばではありますが、試行錯誤してきた過程について皆さんに共有させて頂きたいと思いました。何か個別具体の施策がハマった、劇的な成果が出たなどという華麗な事例ではありません。無駄もあると思いますが、全方位的に少しずつ取り組む中で、個々の施策がお互いにポジティブな相乗効果を生んでいっているのではないかと思います。
皆さんにとって、何かのヒントになるものがあれば幸いです。
【構成】
1.社長として最初にやった仕事は経営方針の明確化でした
2.組織には「伝えているのに伝わらない」という構造がある
3.かつて飲みニケーションが果たしていた役割
4.必要なのは“設計されたコミュニケーション”― 価値観共有の場
5.カギとなるのは“インフォーマルなコミュニケーション”
6.なぜ“インフォーマルなコミュニケーション”が経営課題に効くのか?
7.フォーマルとインフォーマルは「論理」と「情緒」の両輪
8.相乗効果を生む「コミュニケーション設計」
9.制度は“伝える”だけではなく、“話される”ことで意味を持つ
■1.社長として最初にやった仕事は経営方針の明確化でした
別の記事で発信した通り、会社の歴史として、かつて退職者が「絶対選ばない方が良い会社」「漆黒のブラック企業」と転職サイトに残したように、会社本位の社風・文化・価値観があったと思います。(参考エピソード「令和7年度永年勤続表彰式」)その中でカリスマ・指針を失い、同僚が社長になった。これは社員は不安だったと思います。社員たちに対して、まずは社長としての約束事を明示しなければならないと考えました。
私がこの会社で一社員として働いてきて辛かったものを改革すると同時に、JCAの良さを受け継ぎ守っていくことを念頭に、以下の8つの約束を掲げました。
【経営者としての約束】
- (1)社員を大切にします。社員の成長と自己実現の助けとなります。その支援を惜しみません。
- (2)社員とその家族を大切にします。社員が家族に応援してもらい、誇りを持って業務に励むことができるような会社にします。
- (3)社員が食べるために働くのではなく、自分の仕事で社会の役に立てることに自信と誇りを持ち、働ける会社にします。
- (4)売上や規模の拡大を目的としません。雇用を維持し、社員が豊かになるために利益を求めます。
- (5)人出しは行いません。JCAチームとして高い付加価値を提供することにこだわります。
- (6)社員が会社に対し、無用な不安を抱かないように情報を開示します。
- (7)社員が仲間と有機的に結びつき、一致団結して活力を持って働ける会社にします。
- (8)筋道、道理、これまでJCAが大切にしてきたものに照らして物事を判断します。
それから、全社員のJCAに対する解釈をまとめる必要があると考えました。言葉と物差しを合わせるのです。そこで、私の社会人人生を振り返るとともに、会社に残っている議事録を全て読み返し、さらに先輩たちの話を聞いた上で、私が解釈し実践してきたJCAを誰でも理解できるように体系立てて整理し、一冊の本にまとめました。
私たちはこれを「経営計画書」と呼んでいます。B5サイズで110ページ程度あります。「経営計画書」は全社員に配布しています。リーダーである私も含めこの「経営計画書」の方針に従って仕事をしています。
■2.組織には「伝えているのに伝わらない」という構造がある
経営計画書があることで、社員は誰でもいつでも会社の考えや方針を確認可能な状態になりましたが、配って終わりではなく、各自の理解に任せず、内容を深く理解してもらうための仕組みを作りました。
「経営計画書勉強会」と題して、毎月全社員参加で勉強会を開催し、経営計画書の各章をテーマとしてグループディスカッションを行っています。私が解説することもありますが、基本的には社員同士タテヨコナナメで話し合うことで、理解を深めたり新たな発見につながっています。
この勉強会を開始して4年目になりますが、今では、社員一人一人が、私が描く将来の夢に対して共感してくれ、その実現に向けて尽力したいと自分の言葉で語ってくれています。理念や制度が文化として息づく組織へと変化してきたことを実感し、感動しています。
また、採用においては「この経営計画に共感できるか、一員として尽力したいと思えること」を大前提とした上で、その人のパーソナリティや適性を判断することにしています。実際に、2024年に中途入社した社員には、経営計画書を渡し「これを読み込んだ上でなお入社を希望するかどうかを判断してください」と話をしました。新入社員のオンボーディングにも活用されていますし、驚いたのは、とあるプロジェクトを担当するチームにおいて、経営計画書を使った有志の勉強会が行われていたことです。
ここからは具体的に、理念や制度を制定した後、形だけではなくどうやって文化や社風に浸透させてきたのか、私たちの組織改革の実践内容の一部についてお伝えします。
制度を整えても動かない。理念を語ってもピンと来ない――
その背景には、社員が“言葉として聞いた”あるいは“テキストを読んだ”だけで、「自分の言葉として語れる状態」になっていない現実があるかもしれません。
必要なのは、社長と社員、社員同士タテヨコナナメをつなぐための仕掛け。つまり「コミュニケーション設計」です。
■3.かつて飲みニケーションが果たしていた役割
当社はコロナ禍以前まで、全社で月に2回、主任以上で月に1回の飲み会をやっていました。全員参加です。仕事が理由で断ると指導を受けていました。また、この他に年に3回社員旅行を行っていました。これも全員参加です。これを基本として、新年会、新入社員歓迎キックオフ、暑気払い、忘年会…と食を通じたコミュニケーションの懇親会・イベントをこれでもかとやる会社でした。
タフな懇親会文化に嫌気がさして去って行った社員もいましたが、一方そのおかげで社員同士の人間関係は基本的には良好で、会社で開催する懇親会以外にも飲みニケーションが活発な方でした。
私が代表者になった後、もうこのタフな文化はとてもではないが続けられないが、完全に緩めてしまっては、私たちの良好な人間関係も失い、ひいては私たちらしさも無くなってしまうのではないかと思いました。JCAをぶち壊してしまうのではないか。飲みニケーションを通じて、もちろん息抜きすることもありますが、懇親を深める中で先輩が価値観をじっくりと語り、若手はそれを自然に吸収する中で、私たちらしさを醸成していく文化がありました。
私自身、20代の頃は先輩を捕まえては飲みに連れて行ってもらい、いろんなことを教えてもらったことが自分の糧になっています。もちろん、息抜きになり翌日からまた頑張るための英気を養えましたし、先輩たちのことをよく知り、その人柄を好きになりました。好きだからこそ、オフィシャルの場でもついていくことができました。
私は社長として、これまでのように社員たちに飲み会への参加を無理に強いることはできないが、飲み会が無くなったとしても飲みニケーションが果たしてきた機能を補うために、別のことはできないか?というのが発想のきっかけでした。
■4.必要なのは“設計されたコミュニケーション”― 価値観共有の場
そこで、会社の価値観やお互いの価値観、人間性に集中して自己開示・相互理解する場を設け、習慣的に行うようにしました。
「経営計画書勉強会」の場では、先輩達が若手に対して会社の方針や価値観について、自分達の経験を元に、自分の言葉で語りかけます。そして若手の感想や反応から新しい発見をし、さらに理解を深めていきます。
また、お互いの人間性に集中する場として、致知出版社が推進している「社内木鶏会」を導入し、毎月実施することでお互いのことをよく知り、人間力を高め合う場としています。
■5.カギとなるのは“インフォーマルなコミュニケーション”
一方で、食を通じたコミュニケーションについても、金銭面での補助をし積極的に実施することを奨励しています。2024年度の実績では、社員主導の懇親会が120回程度開催されていることが分かり、驚きました。
ちなみに私は、懇親会のことを社内では「みんたべ」と呼んでいます。これは“みんなで食べる”を語源にした新しい言葉です。飲み会や懇親会というと何となく夜×お酒を連想してしまいますが、お昼を一緒にするのも懇親を深めるためには有効です。また、世間一般では飲み会に抵抗を感じる風潮があるのと、何となく洗練された感がないと思い、ネガティブイメージを刷新し、カジュアルで親しみのある響きを持たせたくて言葉を作りました。合言葉は、「みんたべしようよ!」です。
「みんたべ」活動への参加について、当然に無理強いは無くしたものの、私たちはなぜこの文化を大事にし、そのコミュニケーションを通じて、お互いにどうなって欲しいのかということを明示しています。私が社員に約束した一つが、この起点になっています。
JCAメンバーが仲間と有機的に結びつき、一致団結して活力を持って働ける会社にします。
「みんたべ」制度は、フォーマルな施策である「経営理念の制定」とは真逆のインフォーマルな施策の一環として、社員の心理的安全性を確保し、人間関係を良好にし、コミュニケーションのロスを無くし見えないコストを減らすことで生産性を向上する効果が期待できるのはもちろんのこと、理念を浸透し実践していくために行う「経営計画書勉強会」や「1on1」等の制度実行の質を高めていきます。
■6.なぜ“インフォーマルなコミュニケーション”が経営課題に効くのか?
私の捉え方としては、食を通じたコミュニケーションへの補助は、待遇や福利厚生の一環ではなく、社風を良くしていくための投資なのです。現実的な問題として、新入社員が退職した場合の経営的損失は、一人当たり700万円と言われます。リテンションのための人事施策は人手不足で倒産する時代における重要な経営課題です。JCAは年間で数百万円を投資していますが、700万円プラス将来の売上を失うぐらいなら、「みんたべ」にお金を使った方が合理的だと私は考えています。
経営課題は社員一丸となって解決に向けて動かなければなりません。これが待遇の一環と解釈されると公平・不公平の発想に繋がったり、変に不満を感じたりすることに繋がってしまいます。これは社風を良くしてくために活動していくことであり、ひいては会社が儲かって自分達が豊かになるために取り組むことなのだということを、社員全員が理解しなければなりません。個人ではなく、組織のスケールで物事を考えてもらう必要があります。
ただし、投資の効果を最大化するため、「みんたべ」の場がただの憂さ晴らしになってしまってはいけません。これは意義のある活動であることを社内に啓蒙するとともに、私は社員に求める約束として、経営計画書に、例えば次のような項目を記載し、この意図を浸透させています。
【社員としての約束(一部抜粋)】
- (1)JCAの価値向上に貢献します。これに反する行為は行いません。
- (2)無用なネガティブに他人を巻き込みません。他人の邪魔をしません。
- (3)無用にネガティブになりません。前向きに捉えます。ポジティブな表現をします。
- (4)仲間と有機的な結びつきを自ら作ります。良好な人間関係を構築するよう自ら努めます。
- (5)自己責任と認識します。他人のせいにせず、原因は自分に見出し改善します。
そして大事なのは、上の人は特定の人を誘わず、「みんたべ」活動の目的を踏まえて、チームやグループ、全社という単位で適切な範囲に声を掛ける配慮が必要です。
■7.フォーマルとインフォーマルは「論理」と「情緒」の両輪
理念を制度として形にする、評価制度に落とし込む、勉強会で対話の機会をつくる――。こうしたフォーマルな仕掛けは「目的地への地図」を提示する行為に近いと思っています。
しかし、どれほど道筋が整っていても、「その道を共に歩もう」と思える関係性がなければ、人は動きません。だからこそ、フォーマルな仕掛けだけでなく、インフォーマルなつながりが必要なのです。
私たちは、制度や仕組みで論理的に納得してもらう一方で、「この人たちと一緒に働きたい」「この会社で頑張っていきたい」と思える情緒的なつながりをインフォーマルな場で育んできました。食を囲むことは、言葉にしにくい価値観や経験を自然と交換できる場になります。
**「同じ釜の飯を食う仲間」**という表現がありますが、まさにその感覚です。ちなみにご存知でしょうか。英語の「company(カンパニー)」の語源を調べると、一緒にパンを食べる人という後期ラテン語の「companio」に由来すると言います。日本語の「会社」は幕末の頃、英語の「company」の訳語として使われ始めたそうです。藩の会合場所「会所」と、仲間の意味の「社中」を複合させたと言われます。
会社の仲間と同じ釜の飯を食う、これが原点なのかもしれません。
■8.相乗効果を生む「コミュニケーション設計」
ただし、仲良くなることだけを目的としてはならないと思います。目的地を示して行動を揃える決まりを作るだけでも機能しません。チーム皆で同じ方向を向いて、お互いのことをよく知り力を合わせ、言葉と行動を揃えていくことが必要であり、両輪での取り組みが必要だと思います。
フォーマルな制度や勉強会があるからこそ、インフォーマルな場での雑談にも共通の言語が生まれます。逆に、日々の対話があるからこそ、制度の背景や意味が腑に落ちる――。
つまり、両者は独立した別々のものではなく、**お互いを補い合い、強化し合う関係性=“相乗効果”**を持っているのです。
制度は論理で動かし、関係性は情緒で支える。その両輪をバランスよく回していくことが、理念を浸透させ、文化に変えていく仕組みになっていると、今は考えるようになりました。
■9.制度は“伝える”だけではなく、“話される”ことで意味を持つ
制度や理念が“話題になる”“社員が自分の言葉で語る”ようになったとき、それは制度が“文化として根付いている”証です。世の中には、経営理念やビジョン、イズムが溢れています。でも実際、それを“自分ごと”として語れる社員はどれだけいるのでしょうか。
JCAにも古くから「JCAイズム」という言葉がありましたが、定義されたものはありませんでした。「JCAイズムとは何か」と題して話し合いをさせることも多々ありましたが、皆それらしいことは言うものの、何が正解なのかは分かっていなかったと思います。過去、「JCAイズムとは誇りである」と言った古参のマネージャーがいましたが、それでは体現することはできません。
現在のJCAの社員たちの認識を感じてもらうため、今年の4月21日、経営計画書勉強会を行った際の実際の社員の声を紹介します。これは私が読みやすいように要約したものですが、元となる文章は記事の最後に掲載しますので、ぜひご覧ください。
〜
【ベテランの声】
・「リーダー層として、情報を隠さずタブーを作らない。言動で文化を育てたい。」(M 1998年入社・男性)
・「子供の行事に参加できる環境に感謝。私もJCAの発展に責任を果たしたい。」(K 2000年入社・男性)
・「自分の仕事が理念に沿っているか再確認。理想を皆で追い求めたい。」(K 2002年入社・男性)
・「感謝される仕事が喜び。チームの力で成果を出していきたい。」(S 2006年入社・男性)
【中堅の声】
・「価値ある仕事の実現には育成と環境づくりが不可欠。現状維持では前に進めない。」(T 2014年入社・男性)
・「JCAの理想は夢のよう。でも、その実現に向けて尽力したい。」(I 2016年入社・男性)
・「社会に与える価値が自分の幸せにもつながる。理想に共感し実現を目指す。」(I 2016年入社・男性)
・「JCAは伝統を大切にしながら時代に合わせて変化している。」(Y 2018年入社・男性)
【若手の声】
・「今は“人の役に立てる”ことにやりがいと誇りを感じている。」(N 2020年入社・女性)
・「“ユニークさ”にJCAらしさを感じる。もっと広めたい。」(N 2021年入社・女性)
・「社長の想いが少しずつ理解できるように。迷ったときは経営計画書に立ち返りたい。」(N 2022年入社・女性)
・「JCAの歩みを知り、自分も未来をつくる一員だと実感した。」(I 2024年入社・女性)
・「JCAの情熱に感動。福岡に“頼れる会社”があると感じた。」(F 2025年入社・男性)
これからの組織づくりにおいて大切なのは、形だけの制度や施策ではなく、つながりと共感を育む“仕組みづくり”です。
■実例共有会のご案内
このようなテーマについて、経営者・人事担当者向けの当社の実例共有会をセミナー形式で開催いたします。組織改革のリアルな体験や、制度と理念をつなぐ仕組みづくりについて、詳細な実例を交えてお話しする予定です。
【タイトル】
なぜ社長の考えが会社に浸透しないのか?~理念が現場で機能する“仕組み”をつくると、会社は変わる~
【日時】2025年5月27日(火)13:30~15:00
【会場】アクロス福岡 解決市場 会議室(福岡市中央区天神一丁目)
【定員】20名程度を想定(参加費無料)
【講師】平木誠(株式会社JCA 代表取締役社長)
【内容】
・ 理念を掲げるだけでなく、「どう制度に落とし込むか」「どう行動につなげるか」を設計・実践してきたプロセスを学べる→ 自社でも“理念が売上や定着率に効く設計”ができるようになる
・上意下達ではなく、社員自らが理念に沿って動く仕組みを作った実例から、社員を“指示待ち”から“共創パートナー”に変えるヒントを得られる
・なぜ多くの福利厚生や社内施策は失敗するのか?それを回避する構造的な考え方が得られる。バラバラの施策が「一本の軸」に収束し、成果につながる。福利厚生を導入しても「何を大事にしてる会社なのか」が見えない→ 単なるコストに見られ、活用も進まないし下手をすると給料を上げてくれとの声
【対象】
・継続的に従業員を採用しており、採用・リテンション・研修等の施策を模索している
・理念やビジョンは掲げているが、「現場に浸透していない」と感じている
・賃上げ等はすでに自社なりに実施している
・福利厚生・制度導入に取り組んでいるが、「形骸化している」と感じている
・採用活動では理念を訴求するが、入社後の離職率やギャップが課題
・Wantedlyなどで理念採用を行っている企業
・・・制度と人をつなぐ設計に課題を感じている方へ。ご参加をお待ちしています。
▼参加登録
興味がある方、参加申し込みをされる方については、詳細が決まりましたら、改めて個別にご案内させていただきますので、連絡先の登録をお願いします。
登録いただきましたら、送信確認を兼ねてメールをさせていただきます(自動送信ではありません)ので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
みなさまとお会いできることを楽しみにしています。
■社員の声の全文を紹介します
【ベテランの声】
・M(1998年入社・男性 「リーダー層として、情報を隠さずタブーを作らない。言動で文化を育てたい。」)
「今後入ってくるJCAメンバーや私より若いメンバーに対しても、我々リーダー層が情報を隠蔽してタブーな領域を作ることがないよう、指導の言葉や態度に注意して文化として醸成させていかなければならないと思います。」
・K(2000年入社・男性 「子供の行事に参加できる環境に感謝。私もJCAの発展に責任を果たしたい。」)
「社長が家族を大事にする会社を目指されていることで、私も子供の行事に参加する機会が増え、子供の成長を見ながら仕事ができる環境は有難い。そのようなJCAが発展していくために私の立場、職責を全うしていきたいと強く思う。」
・K(2002年入社・男性 「自分の仕事が理念に沿っているか再確認。理想を皆で追い求めたい。」)
「今の仕事を振り返ると、多くの観点で出来ていないことがあると認識した。受託開発においては、お客様からも、メンバーからも、誇りを持った尊敬される存在にはまだ成れていない。各種社内作業においては、細かいところにばかり目が行っており、会社が目指す姿と食い違う活動もある。会社の目指す姿を皆で追い求めなければならないと思った。」
・S(2006年入社・男性 「感謝される仕事が喜び。チームの力で成果を出していきたい。」)
「お客さまから感謝を頂いた時、JCAというチームがお客さまから一目置いてもらえていると感じた時、誰かに頼りにされた時に、仕事における充実感や満足感を感じてきた。今後も誰かに感謝されるような仕事ができるように日々成長していければと思うし、チームで力を発揮できるように結束を固くしていきたい。」
【中堅の声】
・T(2014年入社・男性 「価値ある仕事の実現には育成と環境づくりが不可欠。現状維持では前に進めない。」)
「これを実現するためには付加価値の高い仕事をできるようにならないといけないと思う。さらに、自分の仕事で役に立っていると実感できるように新しく加わったメンバーを育てていくことや彼らを受け入れる環境を創り出すことも必要。現状維持を追いかけていてはこれらのことは実現できないため改めて気を引き締めなければならないと思う。」
・I(2016年入社・男性 「JCAの理想は夢のよう。でも、その実現に向けて尽力したい。」)
「社長の理想は、夢のような世界が語られていると感じる。まだまだJCAは道半ばだが、その実現のために尽力できると思うと、生きる希望が湧いてくる。」
・I(2016年入社・男性 「社会に与える価値が自分の幸せにもつながる。理想に共感し実現を目指す。」)
「社会に与える価値を意識し続けることで、結果的に私たち自身の幸せにもつながる。これが本当のワークライフバランスなのではないかと思う。理想的な会社の姿だと思う。私もこの夢のあるビジョンを実現するために、日々の仕事に尽力していきたい。」
・Y(2018年入社・男性 「JCAは伝統を大切にしながら時代に合わせて変化している。」)
「JCAは変化を厭わず時代に即した形で良い方向に変化していっていると思う。また同時に、佐藤会長の時代から培われてきたJCAイズムを風化させることなく、今までのJCAを尊重しつつ、変化を続けているように感じる。」
【若手の声】
・N(2020年入社・女性 「今は“人の役に立てる”ことにやりがいと誇りを感じている。」)
「私は入社当時、仕事に対して社会貢献の意識や楽しさ、誇りを持って働くというものをあまり考えることができていなかったが、今ではお客様だけでなく、共に働くメンバーに対してもFor Youの気持ちを持ち、人の役に立てることにやりがいと誇りを感じる。」
・N(2021年入社・女性 「“ユニークさ”にJCAらしさを感じる。もっと広めたい。」)
「 『「福岡にこんなおもしろいユニークな会社があるのかと思われるような存在でいる』おもしろさ、ユニークさを大切にしているところに、JCAらしさや魅力が詰まっていると感じる。広く知ってもらえるように活動していきたい。」
・N(2022年入社・女性 「社長の想いが少しずつ理解できるように。迷ったときは経営計画書に立ち返りたい。」)
「以前は難しくてよく分からなかった内容も、今は社長の想いや方向性が少しずつ理解できるようになったと感じている。まだ自分のことで精一杯のことが多いが、同じ方向を向けるように、どうしたら良いかわからなくなった時は、都度読み返したい。」
・I(2024年入社・女性 「JCAの歩みを知り、自分も未来をつくる一員だと実感した。」)
「入社してから1年が経ち、これまでJCAがどれほど厳しい環境の中、今日まで成長し、生き抜いて来たか、先輩方のお話から知ることが出来た。これからのJCAをどう成長させていくか、改めて他人事ではなく、自身もチームの一員として、社長の望んでいる未来を実現させていく使命があると感じた。」
・F(2025年入社・男性 「JCAの情熱に感動。福岡に“頼れる会社”があると感じた。」)
「社長のJCAメンバーに対する信頼と仕事に対する情熱も感じ取れ、感動しました。福岡にこんな会社があるなら、福岡の一住民としてとても頼りになる会社だなと思えたことを思い出しました。私も福岡の人たちと社会にそういった気持ちを持たせる会社でこれから働けることを光栄に思っています。」


