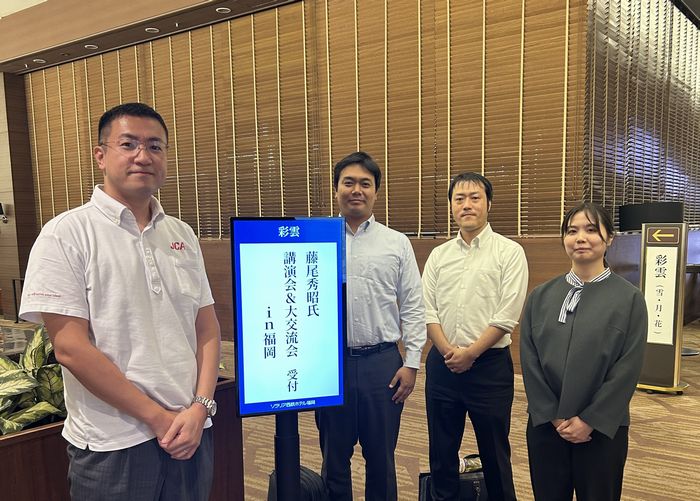先日、ソラリア西鉄ホテルにて致知出版社代表取締役 藤尾秀昭氏の講演会が開催され、当社のメンバー6名が参加しました。今回の記事では、参加したメンバーが全体ミーティングの場で発表した感想をご紹介します。
与えられた環境の不満ばかり口にして環境を変える・逃げ出すような話は良くあるが、やはり何事も見方、捉え方なのだと改めて感じた。自身が一度した選択に関して、そこにただ漫然といる、その境遇を憂うのではなく、そこで自分は何を得ることができるのか、どういった動きをすればより良くなるのか、考え抜き動いて行く。日頃からないものにばかり目をやるのではなく、あるものをどう活かしていくべきかを考えることが、成長・成功に繋がっていくのだろうと思う。
現代では「石の上にも三年」という言葉は古臭く、「転石苔を生ぜず」が良しとされるのかもしれないが、「徹底して信じ、そこに居続けること」というのは仕事という面においても真理のような気がした。 また良い出逢いを手繰り寄せるのは、自身のこれまでの経験であるという話は、上述の内容にも繋がるように感じた。
毎号の致知の中には様々な話があるが、それを漫然と捉えるのではなく、自身に置き換え、得られることを1つ1つ真剣に捉えることも出逢いの1つなのではないかと感じた。自身ではできない多様な体験も、実体験とは少し異なるが、自身の見聞の1つとして蓄えていくことが人としての幅に繋がるのではないかと思うため、より一層意識しながら取り組んでいきたい。
Kさん(マネージャー)
「成人の学」を掘り下げる際、藤尾氏がある大学に講義に行った際のエピソードが添えられ解説されていましたが、講義の時間が近づいても食事をしたり、雑談をやめない、講堂の後方に固まって座り姿勢も良くない、大学の教授が「私の時は良いけども今日はちゃんとしなさい」と語った、というような内容でした。私もそこまでひどくはないものの、耳が痛いところがありました。それでも藤尾氏の講演の中で徐々に学生が前のめりになり、最終的にはしっかりとしたレポートが提出されたのを見て、「平成の時代も吉田松陰の時代も若者が持っている物は同じなのだ」と感じたという話しは考えさせられるものがありました。
1854年、ペリーが黒船で日本に来航した際、日本を背負って立ったのは高杉晋作、吉田松陰、坂本龍馬といった当時の若者たちだったそうです。高杉晋作14歳、吉田松陰24歳、坂本龍馬19歳というような、今の時代では考えられないような若さです。吉田松陰はその後、伊藤博文など様々な要人を輩出してきた教育の天才なのだそうですが、その吉田松陰でも育てることが出来なかった弟子がおり、それは「憤する心」が無かったからだ、ということでした。憤とは憤り(いきどおり)ではなく、感動・感激する心であり、その要素がなければ人は育たない、という話しです。
公演の中では、人は死ぬまで成長をやめることもないと語られていましたが、自分自身は年を重ねるにつれて感動・感激する機会も減ってしまってはいないだろうかということを感じました。平澤興氏の「生きるとは燃えることだ」「教育とは心に火をつけることだ。しかし、自ら燃えている人でなければ火をつけることは出来ない」という言葉にも通ずるところがあると思います。成長する素養を自ら断ってしまうことが無いよう肝に銘じたいと思います。
Uさん(マネージャー)
「人はこの世に生まれてきた以上は、自分のためだけでなく必ず世の中に貢献することが義務である。すなわち人は生まれながらに使命を与えられている。」という話があります。普段の生活や仕事を当たり前のように感じてしまいがちなのですが、致知9月号の特集「人生は挑戦なり」にも通じるように、人間として、日本人として、母親から生まれ、家族や会社、周囲の方々からも生かされている環境にあることを深く受け止め、いち社員として、または家族を養う主として、その使命感を持って、自分の人生に悔いのない生き方をしなければならないと思い直しました。
その上で、講演会で話されていた「憤」という精神、藤尾氏が致知での歩む道の中で掴んだとされる、「発展する会社の条件」や「子供を伸ばすための為の教育の在り方」、「人生を決定づける資質に必要な要素」等、熱く語られている話が印象に残りました。
また、木鶏会での「美点凝視」について、お互いがお互いの素晴らしいところを見つけ、共に尊重しつつ、人間的な成長を目指す活動であることを、もう一度意識しなおし、これからの会社の木鶏会に挑みたいと思いました。
Kさん(リーダー)
かつて数々の英傑を輩出した松下村塾というものがありました。指導していたのは吉田松陰。久坂玄瑞や高杉晋作といった幕末に時代を動かした志士、伊藤博文や山県有朋といった明治を率いた政治家を輩出してきました。 優れた指導者であった吉田松陰であっても、どうしようもなかった門下生が3名いたそうです。松陰曰く、彼らには「憤」がなかった。「憤」とは、憤るだけではなく物事に感動・感激すること。それがなければ、同じ指導者の薫陶を受けていても、大成するかしないかという大きな違いが出てくるそうです。
藤尾氏が以前とある大学で特別講義をしたときに、今も昔も若者の資質は変わらない。ただ違うのは、受け止めることができる力があるかどうかだけだと感じたそうです。その背景にあるのは「成人の学」。人間力を育てること。人間力がなければ、同じインプットであっても活かすことができないということ。一朝一夕に育つようなものではありませんが、継続して致知を通して人間力を育てていくことで、受け止める土壌を育てていくことが肝要です。
講演のタイトルは「出逢いの人間学」でした。人には、必要なときに必要な出逢いがあるそうです。ただ、それに気づくことができるかどうかはその人の人間力次第。必要な出逢いに気づけるように成長していくことが、致知を読むことの狙いなのだと気づきました。
Gさん(リーダー)
想像していたよりも多くの参加者がいて、中には高校生も参加していたことに驚きました。社内木鶏全国大会の様子や学生が実施している学内木鶏会の様子も紹介され、木鶏会はこんなにも広まっていて、私が今取り組んでいることは、日本人として人間として良い行いをしているのだと感動を覚えました。
今回の講演の中では、これまでの社内木鶏会や致知の中で取り上げられたものと一致する言葉や内容があり、社内木鶏会を通して学び取れているものがきちんとあるということを実感することができたと思うと同時に、格物致知という言葉の通り、体で体験して体験を積み重ねるまで本当の意味での学びはまだまだこれからだということを感じました。
「成人の学」の話の中で、日本に黒船が来航した際に、問題意識を持ってペリーに立ち向かったのは、10代〜20代の若者だったのだという話がありました。その話を聞いて時代を感じるとともに今の私よりも若い人たちが、日本全体の行く末に問題意識を持ち、できることを考え実行できているという点に、年齢は関係なく立派な人間になることができるのだということを思いました。
Nさん(入社4年目)
JCAでは昨年10月から「社内木鶏会」(致知出版社の月刊誌「致知」をテキストに、会社内で「人間学」を学ぶ月例の社内勉強会)をスタートし、まもなく1年を迎えようとしています。
当社は『福岡中の「こうしたい!」を私たちがシステムで解決します。』というブランドメッセージを掲げ、事業を展開しています。会社として、単に利益を追求するだけではなく、人としての成長や地域とのつながり、社員とそのご家族を含めた人間関係等を大切にし、様々な取り組みを行っています。人としての成長に向けた取り組みの一つとして「社内木鶏会」を導入しており、メンバーが互いに学び合いながら「人間力」を高めていきたいと考えています。
社内木鶏会導入の経緯等については、以下の記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
社内木鶏会
最後まで読んでいただきありがとうございます。JCAに興味を持ってくださった方は、ぜひLINEからお気軽にお問い合わせください!