当社では、2024年10月から社内木鶏会を開始しました。社内木鶏会とは、月刊誌『致知』をテキストに、会社内で人間学を学ぶ月例の社内勉強会です。(参考:致知出版社)
社内木鶏会導入の経緯
社内木鶏会の導入は、3年ほど前に社長がその存在を知ったことがきっかけでした。会社として導入のタイミングを検討する中で、2024年6月に東京で開催された全国大会に社長が参加し、同年8月には、オガワ機工株式会社様のご厚意で、社長と10名のメンバーが訪問して実際の社内木鶏会に参加し、運営方法や進め方を学ぶ機会を得ました。
これまでJCAでは、月に1度の全体ミーティングで経営計画書の勉強会を行い、会社の理念や方針への理解を深める取り組みを続けてきました。また、新人や若手社員向けの研修として、『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』(致知出版社)を活用し、仕事への考え方やモチベーションを学ぶ機会を設けています。
こうした学びの取り組みが社内に定着してきたことから、2024年10月の全体ミーティングで第1回目の社内木鶏会を実施しました。
社内木鶏会は、業種業界、会社規模を問わず、国内外1,200社の企業で導入されており、継続することで社風が変わり、業績にも良い影響を与えることが実証されています。導入初期には社内からの抵抗が見られることもあるそうですが、JCAでは第1回目から、メンバーが新しい学びを積極的に受け入れ、前向きに取り組む姿勢が見られました。これは、これまでの全体ミーティングや勉強会等の取り組みが、社内に根付いていたおかげだと感じています。
社内木鶏会からの学び
JCAでは目標管理という取り組みを行っています。これは、「『全員でJCAをより良くしていくこと』をコンセプトとして実施する。自分達の力で魅力的なJCAにしていくために、自分自身にできることが何かを考え、行動目標を定義し、目標管理委員会の力を借りてPDCAサイクルを実行していく。」というものです。(経営計画書 5.3目標管理より)
過去には、否定的な評価に偏る傾向が課題としてありましたが、会社全体で取り組みを見直し、良い行動を具体的に伝える評価方法へと改善しました。相手の良い点に目を向けた評価を行うことで、メンバーの取り組みがより建設的で前向きな方向へ進展しています。
社内木鶏会を通じて、「『美点凝視』の精神でお互いがお互いの素晴らしいところを見つめて認め合う」という考え方があることを知り、相手の良い点に目を向けるという点で、目標管理の取り組みとも通じる部分があると感じました。
感想文紹介
先日、1月の全体ミーティングにて、第4回目となる社内木鶏会を実施しました。今回のテーマは「万事修養」でした。推薦されたメンバーの感想文はオフィス内に掲示しており、その中から一部を抜粋してご紹介します。
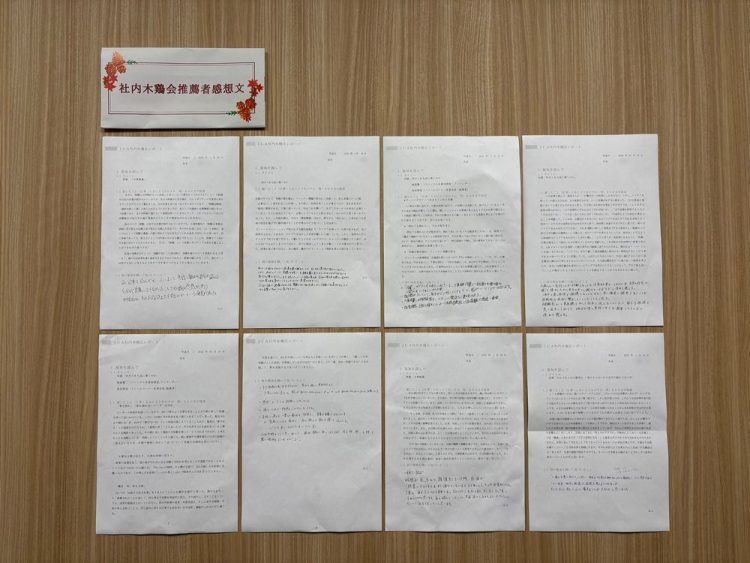
「先達の言葉が示すように、困難な先にこそ道は開け、困難を経たからこそ成長があると思います。様々な出来事を通り過ぎるままにするのではなく、修養の糧とすることで、多少のことは屁でもないと言えるようなタフさを身につけるよう日々努力していきます。」(システムエンジニア 40代/男性)
「『働き一両、考え五両』という言葉は、JCAでの『お釣りのある仕事』をするということにも繋がる話だと思った。指示されたこと、依頼されたことに対して、何も考えず言葉を表面的に捉え、その通りにこなすことをしていても、成果や価値は上がっていかない。指示や物事の背景、本質を捉え、そこに対する戦略・自身の考えを持つことで、同じ指示に対する仕事でも向き合い方や成果・価値が上がるのだと感じる。全体を通して、JCAが大切にしている考え方と合致しているポイントが多く、『厳しくも和気藹々とした会社』を体現しているのではないかと思う。より一層、会社へ貢献できることを目指して、夢を実現する力をつけていきたい。」(システムエンジニア 20代/女性)
「『アイデアを持って一の努力をすれば、五の成果が上がる』とあるが、アイデアを出すこと自体が難しいと感じていた。しかし、鳥羽さん(ドトールコーヒー名誉会長)がフランスで『何でも見てやろう』と動いたことがきっかけでドトールコーヒーが誕生したと知り、分からないで受け止めてしまうのではなく、何でも吸収しようと自ら動くことが大事なのだと気づいた。何事も受け身ではなく、働きかけていくことで現状を変える努力をしていきたい。」(企画・営業 20代/女性)
最後まで読んでいただきありがとうございます。
当社リクルートサイトに来ていただいた方は、はじめに以下の記事をご覧ください。
「はじめに」
「働くことに何を求めていますか?」
「価値観とは」









